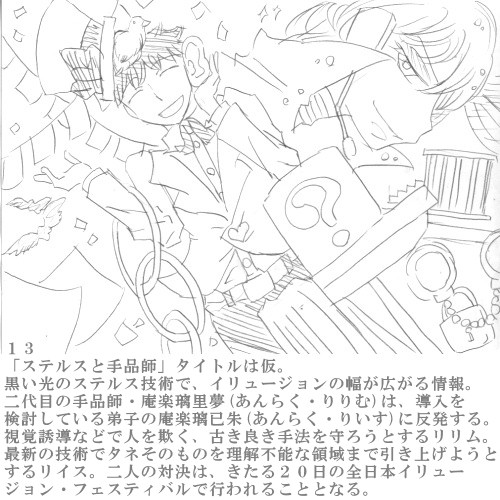■ ズーマクラフト3301 ■
「ズーマ!!」 ドカッと木製のドアを開けて、闇弥マルボロが部屋に入ってきたと同時に、白髪の老人はシルクハットを頭にのせた。 「支配人……まさか、またズーマに?」 老人を見た途端、マルボロの怒りボルテージは最高潮に達し、襟首を掴んで海に投げたいキモチを必死に抑えた。 「いい加減、休暇をとらせたらいかがですか?!ズーマはつい先刻、他の依頼を終わらせたばかりだ!」 「まーまー、マルボロ落ち着けよ」 ズーマは支配人にコートを渡し、クマのできた目を細めた。 「依頼人の前だぜ?」 笑うズーマの後ろには、可愛い女の子とその母親らしき人が居る。二人とも、テーブルに出された紅茶には一切手を付けていない。 「…あぁ、これは失礼」 苦い顔をしてマルボロが依頼人に謝ると、支配人は音もなく部屋を出て行った。 今回の仕事も多分、厄介なコトになりそうだ…と、マルボロは直感で気づいた。 しかし、 「マールゥ、とりあえず座って」 ズーマが比較的元気な笑顔を見せたので 「あ、あぁ…」 一応ホッとしてイスに座った。 昨日の高熱など忘れたかのように振舞うズーマの様子を見て、マルボロは改めて依頼人とクラフト対象者に顔を向ける。 対象者は少女、依頼人はその母親だ。 「娘の病気を治して下さい」 蜂蜜メルッシュと名乗った女性は、自分の娘を見てそう言った。 「クラフト士にしか治せないと伺ったものですから…」 クラフト士とは、国の定める特殊国家資格のうちの一つで、ショウ・カット・クラフトと呼ばれる三段階の魔法技術を用いて、人々のココロの病気を治したり、クラフトイベントに参加したり、国の特殊部隊で秘密工作をしたりできる、今話題の資格である。 この資格には6つのレベルが定められており、ズーマは三番目にレベルが高い「第二種クラフト士」の試験を、史上最年少で受け合格ている。 ちなみに、一番レベルの高い特殊クラフト士から、第一種・第二種・甲種・乙種・丙種と並び、どれも「超難関」とされている。 普通の人には、ショウの工程すらできない。 「んじゃ、娘さんの病状を聞きまショウか? あ、マルボロわかる? 今の、しょうにショウをかけたんだぜ! ぷぷーっ♪」 「……ズーマ…」 頬をピクピクいわせているマルボロを見て、メルッシュは苦笑しながら話しはじめた。 「この子の名前はマドレーヌと言います。昨日8才になったばかりです。三ヶ月前ほどから何も話さなくなってしまって…」 メルッシュは、次第に深刻な声になっていく。 ズーマは「お嬢ちゃんこんにちは」と言って、マドレーヌが何の反応もしない様子を手早くメモに取った。 「最初は、喉の病気かと思いまして病院に行ってみたのですが…治らなくて。しばらくたっても何も話さないので、家の前の通りを歩く荷車の物売りから、箱庭をひとつ買ったんです」 「…箱庭?」 マルボロが身をのりだす。 「えぇ、よく子供が遊ぶでしょう? 箱庭の中に人形を入れて。気晴らしになればと思いまして…そしたら」 メルッシュは娘を見た。 マドレーヌは下を向いたまま、目は虚ろにどこか知らない世界を見つめている。 「話すようになったんです」 「へー。良かったじゃん」 ズーマは他人事のように言った。まぁ、実際に他人事なのだが。それにしても冷たすぎる一言。 マルボロは「構わずに続けてください」とメルッシュに言った。 客をとって商売しているハズのズーマが客のコトを一切考えずこんな調子なので、マルボロはいつも「ズーマの隣で暴言のフォローをしなければ」と思っている。 ちなみにマルボロは、クラフト士でも何でもなく、ただズーマの隣の部屋に住んでいる好青年である。 メルッシュは続けた。 「話すようになったのは良いんですが…、この子が話すのは箱庭に向かってだけなんです」 「うわっ、キショ」 「ズーマ!!」 マルボロは何とか引きつった笑みを作り、イスの上であぐらをかいているズーマの足をキリッとつねった。 「いっ?!」 ズーマは一瞬顔をゆがめ、それから恨めしそうにマルボロを見た。 「チッ。…あー、ハイハイ。やればイイんでしょ。ったく…これだから貧乏学生は…、えーっと、メルッシュさん?」 「ハイ」 「ちょっと午後まで娘さんをお借りしてもヨロシイでしょうか? こっちも色々と調べたい事がありますんで…」 次の言葉はマルボロが続けた。 「用事が終わりましたら、こちらの方で娘さんを家まで送ります。依頼書に書いてある住所でよろしいですか?」 「オレのセリフとんなよ!」 「とってませーん」 どうやらマルボロは「貧乏学生」という言葉にカチンときたらしい。 白々しく顔をそむける。 「オレの仕事!!」 「知りませーん」 「こ…のッ出てけ!!!」 「じゃぁ、お前が壊した俺の部屋の壁修理代は?」 「う…、それとこれとは…」 「払ってくれるんですかぁー」 「……うぅぅー…」 一連の口論を見ていたメルッシュは、苦笑しつつ「前金です」と封筒を置き、部屋を出た。