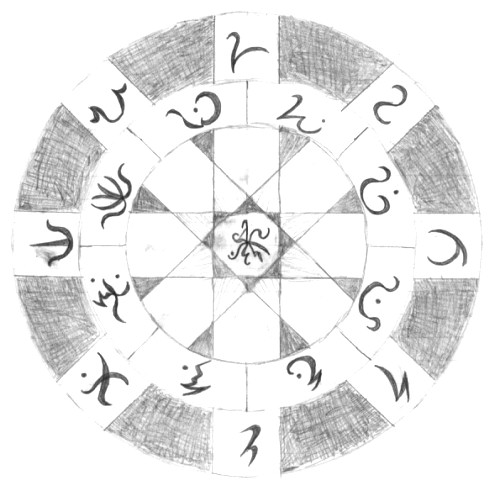■ キセイジジツ ■




敵を倒して皮をなめす! →牛皮小物作品が増え、戦隊の維持費に。
レッド:跡を継いだばかりの新人。
ブルー:作家然としたオバサマ。
イエロー:3・4年前から入った子供。
グリーン:ムキムキの職人。
ピンク:1・2年前から入ったオカマ。
ギックリ腰になった老人レッドのかわりに、新しい戦士が必要。
そこで選ばれたのは、レッドの孫である引きこもりニートであった。
若レッドが入るまでは、臨時でピンクがレッドの役割をやっていたため、まっさきにピングがガチギレ。
まだ子供のイエローまでもがレッドを格下認定する。
ブルーおばさまだけは優しく接してくれたが、裏でこきおろしている所を立ち聞きしてから、レッドが基地に来なくなる。
そこをなんとかしたのがグリーンで、だんだん立ち直っていくレッドの成長物語的ななにか。
忘れ去られたような空。
濡れたサンカクの椅子。
レンガを踏み台に飛ぶ。
ヒルガオは笑っている。
立てつけの悪さできしむ灰色のドアを、強引に、押し倒すように開け放つ。真昼ヶ丘紫朗は振り返った。受付という札が立っている机をはさんで向かい合った近藤は、薄笑いをうかべて言い放つ。
「もう二度と来るんじゃねえぞ、ヒルガオ」
「来るか!」
紫朗は叩きつけるようにドアノブを閉めた。
無骨に続く、暗い階段の下。出口からは長方形の光が、紫朗を別世界へと誘うように手招いている。
腹いせともとれる大きな靴音を鳴らし、光の向こうに出たはいいものの、そこは別世界などではなく、紫朗の気など知らないスーツ姿の人々が行き交う、昼のオフィス街でしかなかった。
探偵事務所で働く近藤は、紫朗の、高校時代の同級生であった。
久々に連絡がきたと思ったら「おまえの嫁さんが素行調査を依頼しにきたんだがな」と開口一番。
三万で依頼拒否。
五万で捏造。
さきほど事務所内で叩きつけた五万入りの茶封筒が、紫朗の頭をかすめる――あいつ、あの金で今夜は豪遊するんだろうな。
誰かと肩がぶつかる。事務服のOLが小声ですみませんと謝った。睨みつけると背中をまるめ、逃げるように去っていく。
「チッ、」
唾を吐き、転がってきた空き缶を踏みつぶし、悪態をついてはみたものの、気は晴れるどころか曇天である。妻の真昼ヶ丘優子の顔がうずまき、重く、のしかかったままだ。
会社のホワイトボードには、社外接待の後、帰宅と書いて出てきた。愛車のエンジンをかけると、紫朗はハンドルを、自宅とは反対の方向へ切った。中心街を抜けるととたんに片田舎のように、田んぼと山が並びはじめる。
選んだCDは曲目が書かれていない鈍色の銀盤だ。信号待ちの合間に入れる。
最近の、妻の様子を思い出す。どこかよそよそしく、そわそわしている風にも見える、と紫朗は思った。
素行調査の事さえ知らなければ違っただろうかと自問する。
少年はビル・エバンスの事を知っていて、わざとギルと呼んでいた。
そう、ヒルガオ。
よくわかったね。
ぼくはギル・エヴァンスの中でもアリスの演奏が一番好き。
ぼくとちがってあんなにロマンチックで……。
三角の風変りな椅子に腰掛け、足をぶらぶらさせながら少年は、それきりだ。
キルキッシュ・ガーデンは光にあふれ、けれど少年にはいつも暗い影がまとわりついていた。
それを伝えると、美しい角度で微笑みながら決まって、こう言う。
オーケイ、ヒルガオ。
じゃあぼくを笑わせてみなよ。
――もう笑ってるだろう、エンデ。
ここはアリスの庭のようだった。忘れ去られて手入れもない、伸び放題の花たちは雄々しく、今にも喋りだしそうだった。時が止まったかのように、雲は動かない。
ぼくの墓地だ。
ぼくはここに眠ってる。いつでも来ていいよ。
空は切り取られ、だれからも忘れ去られている。
エンデと遊ぶいくつもの退屈しのぎの中で、ヒルガオがいちばん気に入っているのは懺悔ごっこだった。
手作りの花冠は、ひきちぎったツユクサの紫で濡れ、三角イスの上に仰々しくエンデが立ち上がると、残酷な事に花弁はすげなく落ちた。
その辺からひっぱってきたブルーシートをまとい、エンデは神のまね事をする。
ヒルガオは、せっかくの洗いたてのシャツを土で丹念に汚し、浮浪者を装った。
神よ!
ワタシは父と母を殺しました。
とびきりうまい罪を思いつかないときには、エンデは決まってこう言えとヒルガオに命令した。ヒルガオの頭に手をのせ、許すとつぶやくエンデの顔はいつも曇っていたが、それはヒルガオの錯覚かも知れなかった。
閉じたまぶたの向こう側が見えるのは、この場所にはなにひとつ動くモノがないからだろう。
キルキッシュ・ガーデン。
名前をつけたのはエンデだ。
ぼくはキッシュが好きだから、と少年はいたずらっぽく瞳を細めた。それも、ほうれん草のね。
でも夜に笑っちゃいけないよ。
声も、たてちゃならないんだ。
緑髪銀色の目の紳士。 使用凶器はピアノ線。 殺害人数は33人。 殺害後、健康な臓器を知り合いの医師を通してドナーの物として使っている。
殺されかける悪人に向かって「仕事とは、誰かの役に立つことで金銭を得る事です。貴方は初めて――(無慈悲な音)―誰かの役に立てるのです」とか言いそう。
表向きの仕事は総合病院の中の1Fにある喫茶ルームの店員。特に長期入院している障害がある人たちを愛しく思うので辞める予定はない。看護婦や医師たちとも親しくして情報収入してる。愛しいあの人に笑ってもらうために臓器移植環境を整えるが、健康になると何故か興味を失ってしまう性癖無自覚者。
巷を騒がせている殺人鬼は、通称「キャトル」。死体は、全身の血液を抜かれた状態や、外側の皮膚と骨を残して内臓を抜き取られた状態で発見される。宇宙人の仕業とされるキャトルミューティレーションからワイドショーの中で名付けられた。
協力している医師の名前は百村修一(モモムラ・シュウイチ)K大医学部医学科出身。喫茶店員とは一度も話した事がなく、そもそも喫茶ルームに立ち寄った事もない。自分の飲み物はマイボトルの番茶。救える命は違法な手段でも救いたい思想の持ち主。キャトルとはK大時代の同窓。
殺人鬼がうろつく魔の都市の中央に、生を至上価値とする総合病院が建っている。そこには、宇宙人ではないかと噂される殺人鬼と臓器移植の天才医師が住んでおり、二人は十年来の親友である――。
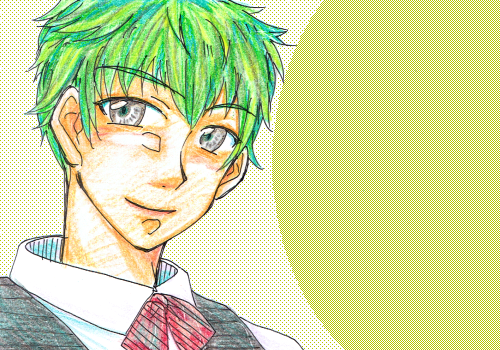
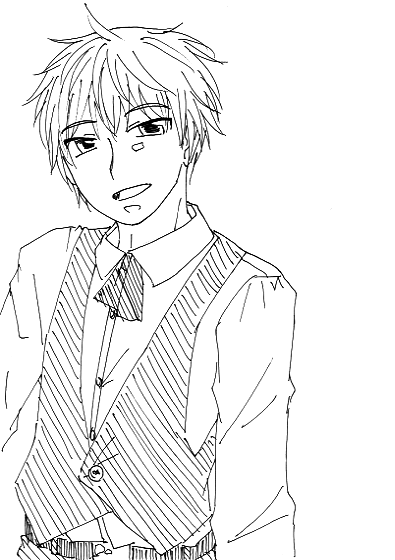

主人公と平行世界の主人公が、交換日記をはじめる。世界の境目には、境界線がひかれており、どちらも夢の中でしかたどり着けない。
ニュースタイルの安楽椅子探偵、ここに登場!安藤三咲は亡き父の遺言を頼りに、鴨黙庵の桜音山聚楽(おとやま・じゅらく)を訪ねる。しかし、廃屋となったそこに住んでいたのは、ホームレスの三川というデブだった。
安藤が困っている事件は、ずばり父の死であった。死ぬはずがないのだ。自殺なんて……。
事の顛末をきいた三川は、座っていた椅子から立ち上がった。
彼は一体何者なのか?
そして父の死の真相は。
全知全能の神の生まれ変わりである神知さくらと、さくらを君主とする能力者たちが集う話。
さくらの幼馴染であるフーキもまた、風の能力を持つ使徒のひとりだったが、その記憶はかたく封印されていた。
高校で出会った同じクラスのミノルと、喋るリスによってその使命が知らされるが、フーキの記憶は中途半端に戻り暴走する。
果たしてさくらは、仲間を探し出し世界の救世主となれるか。