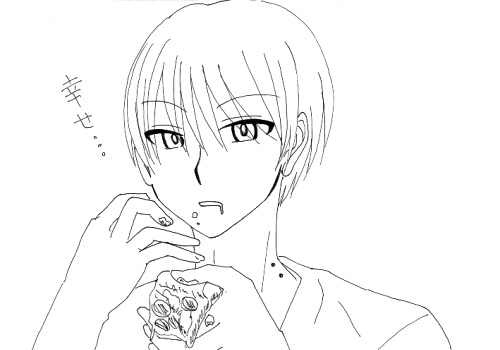■ 水野類はピザ食べたい ■
俺は軟禁されている。
世界を滅亡させないために。
お社の前に捨てられていたのは、俺が禍(マガ)を引き寄せてしまう体質の持ち主だからだ。小さいころからずっと言われ続けてきた。禍は俺自身をも危険に晒すため、拾われてからずっと、社の本殿奥にある小屋に軟禁されている。
とはいうものの、なんだかんだで俺も一般的な大学生にまで育った。
VRゴーグルを付けてネット大学に毎日登校しているし、込み入った話は教授と電話するし、バーチャル空間で友人達と遊んだりもする。気心が知れたらZOOMで顔見せあいながら飲み会したり。けっこう充実した毎日だ。
厳しい修行を経て、禍の呼び込み具合もある程度はコントロールできるようにもなったし。
ただ。まぁ。完璧じゃあない。
この間もホラー映画でビビッて大きな地震を起こ……。……はぁ。
こんなモノローグを独り言のように呟いていてだんだんテンションが下がってきた。手を伸ばし、机に散らばっているチラシ束からピザ屋のチラシを取る。こんな気分の時は、ピザに限る。
表面にはでかでかと、カニのマークが描かれている。
「……カニ、か」
この時期はどこのピザ屋でもカニを推してきている。
カニの旨味がぎっしり詰まったカニとエビのピザ、カニの上にウニクリームを乗せた濃厚ピザ、カニピザと定番のマルゲリータを合わせたハーフ&ハーフ。しかも今なら、カニ系を頼むとガーリックシュリンプ&ポテトのグリルが無料プレゼントらしい。
俺はスマフォの充電ケーブルを外し、ピザ屋に電話した。
『――お電話ありがとうございます。ピザコッテ出雲大社店です』
「あ、もしもし。ピザの注文お願いします。えー…っと、ベストクォーターのMサイズと、竜田チキン5個。以上で」
『そちらですと、あと100円でお飲み物がつくお得なセットがございますが……』
「じゃあ、コカ・コーラZEROで」
『かしこまりました! ありがとうございます』
住所を伝えて電話を切った後、つい、いつものベストクォーターを頼んだ事に気づく。
まぁいい。カニは次の機会だ。
俺はいつものように立ち上がって筋トレを始めた。こうして無心で筋トレをしながらピザを待っていると、余計な禍を呼ばずに無事ピザが届く。経験則ってやつだ。
しばらく筋トレに集中していると、インターフォンが鳴った。
届けてくれたのはピザコッテのアルバイト――ではなく、社務所で支払いを済ませてくれた庶務の石飛さん。
もう一度インターフォンが鳴ってから、窓の下に設置された引き出しを引く。入っていたのは、ほんのり温かいピザの箱と竜田チキンの小箱。そしてコカ・コーラZERO。
さっそく机のチラシどもを退けて、ピザの箱を真ん中に置いた。隣にフタを開けた竜田チキンを置いて、反対隣にはコカ・コーラZERO。完璧な配置だ。
台所で手を洗い、精神統一する。
机の前に正座して、そうっとフタを開けるー…! たとたんにチーズの香りが部屋中に広がった。胸いっぱいに吸い込み、俺は改めてピザを見下ろした。
ベストクォーターのラインナップは次の4種類だ。それぞれ2切れずつ入っている。
まずは王道のマルゲリータ。
次に人気の照り焼きチキン。
箸休め的なチョリソー&コーン。
そしてとろける5種のチーズミックス。
やはり最初は王道からだろう。1時の方向にあるマルゲリータを持ち上げる。一口食べると、熱いトマトとチーズが舌の上に躍り出た。
「あっふ!」
あわててフタの裏にマルゲリータを置き、コカ・コーラZEROのキャップを開ける。一気に半分まで飲んでしまった。
だがそれもいい。
もう一口いく。次はバジルも口の中に入ってマルゲリータを完成させてくれた。トマトの酸味とバジルの苦味を濃厚チーズが包み込む。最高。
次は照り焼きチキン。マルゲリータにはない肉々しさがたまらない。控えめにかけられているマヨネーズは、もっとあってもいいと思う。今度トッピングであったら頼んでみよう。
一度竜田揚げでマヨ成分を消してから、飲み物で完全に消す。そこからチーズにいってみよう。チーズは熱いうちが美味しい。2切れを同時に持ち上げてパタンと折る。そして一気に頬張る! とろ〜りと流れ込んでくるチーズの旨味。口の外側に残ったピザを引くと、チーズの束がトロンと糸をひいて離れていく。限界まで伸ばしたところで、再度口を開けて糸状のチーズだけを食べる。美味い。
チーズ2切れを完全に食べ終わったところで、チョリソー&コーンに移動する。コーンを丁寧に噛んで小さい甘みを広げていく。チョリソーは少し辛めだ。この組み合わせは飽きることがない。竜田揚げも一緒にしてボリュームを足してやる。
ちょっと飲み物で喉を潤してから、照り焼きチキン、竜田揚げ、チョリソー&コーン、竜田揚げ、という風にくり返して腹を満たしていく。最後はマルゲリータで閉めたいから、残った竜田揚げ一個を口の中に放り込む。今日の竜田揚げは当たりだ。新しい油で揚げたと見えて、カラッとサクッと美味しすぎる。
俺は立ち上がり、冷蔵庫から新しいコカ・コーラを取り出した。立ったまま一気に飲む。口の中は冷えて完全にリセットされた。一息ついて机の前に座る。フタを持ち上げ、マルゲリータを頼むとついてくるバジルソースをフタから剥がした。この時のために残しておいたのだ。全部振りかける。
そして持ち上げた最後の1切れを恭しく持ち上げ、ゆっくりと口に運んだ。バジルソースのおかげで、最初に食べた時とは全く違う味だ。静かに食べきり、指についたトマトソースを舐めとった。
完っ食。今日も美味しかった。
しばらくベッドのふちにもたれて幸せなお腹をさする。
と、急に着信音が鳴り響く。ピザについてきたナプキンで指を拭いてからスマフォの画面を見ると、権宮司の多久和さんからだった。今日はまだ何も事故災害起きてないらしく、急に心配になってきたらしい。
「……ピザ食ってたんで」
電話を切ってから、今日ぐらいは多久和さんを安心させてあげようかなと思って、次の食事用のピザを注文してから筋トレを始めた。

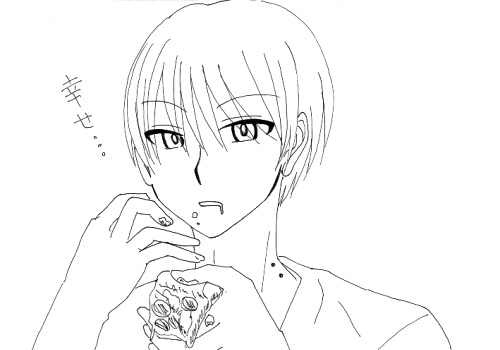
■ 三つの願い ■
女子高校生アイコの部屋には、可愛いヌイグルミなど一切ない。本棚にぎっしり詰まった本。勉強机の上にも、本。窓際には申し訳程度に、また本。本人いわく「THE・書斎」を目指したという、実質ただの本倉庫部屋で、ミユキとアイコはアイスを食べていた。
二階の部屋にあがる前、二人はアイコの母親に呼び止められ、お菓子やお茶は要るかとの問いに揃って「アイス!」と言ったのだ。
「――…で? その魔人って、どうやって呼びだすの?」
ミユキは食べ終わったアイスの棒を噛みながら聞いた。
勉強机の椅子に座っていたアイコは、キイ、と椅子を回転させると、
「ふっふふ〜、コレです! じゃ〜んっ」
一枚の紙をかかげた。その紙には、魔法陣が描かれている。
「お供え物してさ、魔法の呪文をとなえると魔人が出てくるらしいンだよね。ンで、三つのお願いごとを叶えてくれるんだって! あの本に書いてた!!」
ビシッとアイコが指をさしたのは、本棚の真ん中。ミユキが探すまでもなく、目立つようにスペースをたっぷり取って置かれていた。表紙には『世界召喚術大全〜これ一冊であなたも召喚士に〜』と書かれている。
「だからミユキも一コだけお願い考えていいよ。あたしはね、ん〜とね、今ほしい本……っていうか、全集でお願いすれば十冊とか一気に手に入るからぁ〜、あ、でも絶版になってる本もいいよね、なんか、迷っちゃってさ。ミユキは? どう? なんかある?」
「んー…、まぁ、ユメがあっていいんじゃない? あ、アイスは?」
「もう食べた」
勉強机の上には、アイコが食べたイチゴ味のアイス棒。
「う、一口もらいたかった……暑い…、下行って氷水もらってきていい? 先にやってていいから」
「いいよ。お母さんキッチンに居ると思うから」
「うん」
フラフラと部屋を出ていくミユキ。
アイコはさっそく紙を床に置き、手を組んだ。立ちヒザのままうつむき、呪文をとなえ始める……なんとなく自分に魔力があるんじゃないかという気になってきた。――本当に出てきたらどうしよう……何をお願いしようかな……。などと妄想しつつ、暗記した呪文を全て言い終わるころ、部屋の外からトントンと階段をあがる音が聞こえ、ドアが開いた。
直後、
「あっ!」
「いったっ!」
アイコの背中にミユキのヒザがぶつかり、ミユキが転んだ。
ガシャン、と食器が落ちる音。魔法陣の絵の中に、大量のオレンジシャーベットがベトリと乗った。
それを見た瞬間、アイコは目をカッツと開いた。そのオレンジシャーベットは四国限定のお取り寄せ品で、今日の夜に食べようと……大事に…大事に……――お母さん!! 思わず叫んだ。
「アイスううぅぅッ!! アイスっ、あたしのアイスううぅぅッッ!!」
『――承知した』
煙とともに魔人が現れ、ポポポンッと音をたててアイスも出現した。
アイコが食べたイチゴ味の棒アイス。ミユキが食べたソーダ味の棒アイス。そして、ミユキが落とした四国限定オレンジシャーベット。
魔人はフッと消え、アイスはキンキンに冷え、二人は茫然とし、カラスが一声鳴いた。暑い、残暑の夕暮れ時であった。
■ みどりさん ■
みどりさんが言う。
私は若い、と。
みどりさんのシワだらけの手に、僕はハイハイと言って手を重ねる。
とにかく介護の現場は大変で、人がいないのもそうだけれど、お年寄りたちの言葉をきくのも疲れてしまう。最初のうちは何回か質問したり大げさに驚いてみたり、笑い転げた時もあった。けれど、じきにそれも聞き流すだけになってしまい、昨日も今日もおとといもきっと明日も繰り返される同じ話に、反応さえ面倒になってきている。
けれど、みどりさんだけは。
私は若い。そう、みどりさんは言う。
みどりさんは、僕が担当しているお婆さんだ。3カ月くらい前に入所してきた。私はまだボケてなんかいないのに、と泣き始めた時はどうしようかと思った。
「息子たちは私を捨てたのよ、ここに……」
そんな言葉をきくと、僕は苦しくなってしまう。
みどりさんは僕のおばあちゃんに似ている。
もう、いないけれど。
僕はどんなに後悔したか知れなかった。最後に僕がおばあちゃんに言った言葉を思うと……。
「みどりさん、そんな事言うと僕と会えなくなっちゃうよ」
「あらあら、それはいやだわ木村君。木村君に会えないなんて、私、おじいちゃんを亡くしたときよりショックかもねぇ」
みどりさんが笑う。
はずみでこぼれたヨダレを、つい手癖で拭いてあげようとすると、みどりさんはやんわりとした手つきで僕の腕をおろし、自分でティッシュを取りに行った。
みどりさんが一番おそれていることは、三塚さんに名前を呼ばれる日がくるかも知れないことだった。
ここでは「ベテラン」と所員に慕われている三塚さんは、もうどうしようもなくなったお年寄り専門、の、ような雰囲気があったから。僕なんかは、まだ半年くらいしかここにいなくて、現場の事も、まだまだ分からない部分が多い。比較的簡単な人々を任せられる。
僕が担当している老人の、世話の中では、みどりさんが一番簡単だ。
散歩するだけでいい。
部屋の掃除も食事の準備も、みどりさんは全部自分でやる。
よくみどりさんと庭を散歩すると、僕は時々、僕に本当に恋人ができたような……そんな錯覚に陥った。みどりさんは言葉通り、若い心をもっていて、色んなものに驚くし新しい知識も懸命に取り入れようとする。
「木村君、それは――子供心に還っているだけよ」
と、三塚さんは警告する。
「しっかりしすぎないで。適度に、適当にしないと」
お年寄りの言葉を真に受けてしまううちは、まだまだ仕事に慣れていないということなのだそうだ。
そして、その日は案外早くに訪れた。みどりさんの部屋に朝の挨拶と掃除に行くと僕は、彼女に、あなたは誰だと言われてしまった。
「あなたは誰? ダレダッタカシラ……」
みどりさんが屈託のない顔で、瞳で、僕は、どうしようもなく泣きたくなって、みどりさん、と、つぶやいた。
みどりさんは若い。もう子供に戻って、僕の知らない、子供になって。
■ 満ち足りすぎている愛 ■
男が一人、真冬の墓地に佇んでいる。
盆や正月などの時期は既に外れているが、墓参りだろうか。
黒いコート。カシミアのマフラー。左手には花束を持っており、その薬指にはシルバーのリングが、控えめに輝いている。
「ミチヒ……」
男はつぶやく。
かつて強欲に愛を欲した女の名を。
「……っ、いい加減、取ってくれたっていいだろ?!」
天に向かって男はあらん限りの大声でそう叫ぶと、花束をバサリと
墓の前に投げ捨て、雪が降り始めた細い道をとぼとぼと帰り始めた。
★
「係長、コピー終わりました!」
「……ご苦労さん」
社員が忙しく行き来する社内。デスクに座っていた男は、立っている後輩OLの手からコピーした書類を受け取った。
手に手が触れないよう、慎重に首をかたむけながら。
彼は商社の営業マンとして数年働き、今季、係長に異例の昇進を果たしたばかりである。自分と同じ立ち位置で働いていたハズの同僚に、いきなり『ご苦労』などと上からものを言うのは憚られたが、彼女はニッコリ笑って
「係長、今日も直行でご帰宅なんですか?」
と、なれなれしく彼に聞いた。
彼女は今までの関係性を保とうとしている。
「あぁ、まぁね」
ひきつった笑みをうかべながら、彼は心の中で彼女に叫んだ。
本当は、君と一緒に食事やあんなことやこんなこともしたいんだよ!
できれば結婚して、子供も作って、幸せにー……なぁ。
好きなんだ、君のことが。
しかし彼女に届くわけもなく、毎回のお世辞でしめられる。
「本当、係長って奥さん想いなんですね!」
男は、書類を持ったままの自分の手に目をやる。
左手の薬指には、シルバーのリングが嵌っていた。それは男の妻が死ぬ前、最後に指で触れた場所でもあった。
だが。
男は、妻を愛してはいなかった。
死んだ妻・ミチヒが、数十年と勝手につきまとい、無理やり婚約を迫ったのだ。中学からこちら、逃げようとすると彼女専属のSPたちに捕まり強制的にデート。休日も両親にとり入って無理やり家にあがりこむ。淡い恋心はことごとく破壊され、童貞のまま社会人になって数年後。既成事実を作らされ、そうした挙句、結婚させられたんだ!
ミチヒが死んで清々したというのに、指輪は、外れないままだ。
男は、よほどお祓いにでも行こうかと思った。しかし、どうせ事の顛末を話したところで、誰も祓ってはくれないだろう。
上辺だけ聞けば、やはり、ミチヒの愛ということになるのだから。
「はぁ……、」
むせかえるような喫煙ルームでコーヒーを飲み、帰宅の準備をする。
よく、妻が死んだ部屋は広く感じるとかなんとか言うが、正直、一人きりのマンションは、静かで落ち着くと男は思った。
望みに望んだ幸せな生活が、やっと男の手の中に戻ってきていた。
しかし、外れないものは外れない。
ペンチを器用に使い傷をつけてみても、やすりで削っても、朝昼晩と時間帯を変えて引っ張ってみても、石鹸で滑らせてから抜こうとしても、どうしても取ることができない。
男はダイエットにも挑戦してみた。指を細くするためのエステに行ってみたりもした。彼の給与の殆どは、この指輪を取るために費やされた。
意気込んでお祓いにも行った。しかし、案外すんなり祓ってくれたものの、効果はまるでなかった。
「係長……」
「ほへ?」
まぬけな顔をして頭をあげると、深刻そうな顔をした彼女が居た。
一瞬、ミチヒと見間違えた自分がふがいなく、男はブンブンと頭を振った。
居眠りを指摘されるのではないかと肩をすくめたが、彼女の口からこぼれたのは、意外な一言だった。
「あの……相談があるんですけど、今夜、一緒にお食事でも……」
「…………」
「係長?」
「あ! いや、あー、うん、うん、そっか、わかった」
食事は、彼女が選んだレストランで食べ、そして相談は、大した用事でもなく、彼女は「酔ったみたい」と言い、そうして着いた、ラブホテルだった。
夢のような展開に彼は驚きつつも、彼女がシャワーをあびている間にもまだ、男は指輪を取ろうと悪戦苦闘する。
ミチヒは死んでいるとはいえ、普通、不倫というものは、指輪を取るのが定石の筈だ。
しかし、取れない。
ため息をついて諦めたところで、ふと、彼女がこちらを向いて立っていることに気がついた。
「指輪……とらないんですね」
「えっ……」
「さっきからあたし、ずっと見てました。何度も取ろうとして、でも幸せそうな顔であきらめるところ……」
「いや、違っ、これはー……」
「やっぱり、奥さんの方が大事なんですね……っ」
彼女から、大粒の涙がポロポロと零れ落ちる。
違うんだ、と、言ってみても、ますます彼女の勘違いは深くなるばかりであった。
結局何もせず夜は終わり、翌日、彼女は辞表を提出した。
★
「……ミチヒ…」
時期はずれなのだが。
男が一人、墓の前に立っている。黒のコートに、カシミアのマフラー。指輪がはまった左手に、少しばかりの花束を持ちながら。
彼は叫ぶ。
今も、自分からの愛を欲している、天国の憎い彼女に向けて。
「いい加減、取ってくれていいだろ?!」